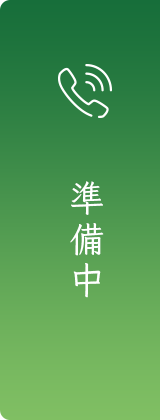年をとっていくたびに増えてしまうのが“もの忘れ”です。私たちの記憶力は30歳から40歳をピークにして、その後はゆっくり低下していくと考えられており、もの忘れは加齢を伴ってどなたでも経験します。ただ、このもの忘れには、年齢相応に起こってく生理的なものと、軽度認知障害(MCI: Mild Cognitive Impairment, 健常と認知症の中間段階)や認知症の初期段階といった病的なものが存在しますので、その原因を見定める診断がとても重要になります。認知症の有病率は年齢とともに高まることが知られており、高齢化が進む日本においては65歳以上の認知症の数は約600万人(2020年現在)と推計され、2025年には約700万人(高齢者の約5人に1人)が認知症になるとも予想されています。
病気によるもの忘れであっても、早期発見で適切な治療につなげられ、回復を期待できるものもあります。アミロイドβ蛋白の蓄積によって生じるアルツハイマー型認知症では、近年、抗体医薬品が開発、上市され、症状の改善や進行抑制が期待できます。
当院では「病的なもの忘れ」を早期に発見し、適切な治療につなげられるように、神経心理検査と診察による診断を行い、その後の治療の選択肢をご本人とご家族へご提案いたします。
また、新規医薬品の適応に至らなかった場合も、適切な治療の継続や環境整備をすることで、患者様本人ならびにご家族が安心して生活できるようお手伝いをします。
もの忘れの種類
- 年齢に伴う生理的なもの忘れ
- 軽度認知機能障害(MCI: Mild Cognitive Impairment)
- 認知症(アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症など)
- 回復する可能性のあるもの忘れ(アミロイドβ蓄積性認知症、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、うつ病など)
加齢による生理的なもの忘れと、認知症の症状としてのもの忘れの違いは、もの忘れを認識(自覚)できているかどうかです。たとえば、生理的なもの忘れは「食事をしたことは覚えているが、何を食べたのかを思い出せない」というものです。対して認知症は「食べたこと自体を思い出せない」といった違いがあります。
下記のようなもの忘れの症状は、認知症の初期症状の可能性があります。このような症状がみられたら、一度、検査を受けることをおすすめします。ご自身では気づかないことも多いため、周囲から受診をすすめられた時にも気軽に検査を受けるようにしましょう。また、ご家族に下記のような症状があった場合、ご本人が抵抗なく受け入れられるように配慮しながら、受診を促すようにしてください。