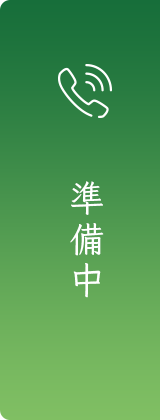強迫性障害は、自分の意思とは関係なく、繰り返し浮かんでくる考えや感情(強迫観念)や、それに対処するために繰り返してしまう行動(強迫行為)に悩まされる病気です。この障害では、自分の考えや行動が過剰(いきすぎ)であると意識では理解していますが、それを抑えるのが難しいとも感じます。
例えば、「手が汚れているかもしれない」という強い不安が頭に浮かび、それを消すために何度も手を洗うという行動は典型的例です。また、「ドアをちゃんと閉めたか」や「ガスの元栓を閉めたか」といった不安から、何度も確認を繰り返すこともあります。これらの行動は一時的に安心感を得ることができても、再び不安が生じ、同じ行動を繰り返す悪循環に陥ることが多いです。
強迫性障害は、日常生活に大きな影響を与えることがありますが、適切な治療で改善が期待できます。この病気には、本人に自覚があるだけに、特殊な辛さがあります。専門家の支援を受け、早く楽な状態を目指すことをお勧めします。
強迫性障害の原因
強迫性障害の原因は完全には解明されていません。遺伝的要因として、強迫性障害を持つ家族がいる場合、発症リスクが高まることがわかっています。これは遺伝的な脳の機能の違いに関連している可能性があります。脳の異常では、セロトニンという神経伝達物質の働きに問題があることが示唆されています。また、前頭葉や基底核といった脳の特定の領域の機能異常が、強迫観念や行動の制御困難に影響を与えている可能性が指摘されています。環境的要因として、幼少期のストレスやトラウマ、大きな生活の変化などが、強迫性障害の発症を引き起こすことがあります。これらの要因が単独または組み合わさることで発症リスクが高まると考えられています。
強迫性障害の治療
強迫性障害の治療には、まずは、薬物療法が用いられます。十分な用量のSSRI(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor: 選択的セロトニン再取り込み阻害薬)が必要となることが多いです。適宜、ベンゾジアゼピン系抗不安薬用いたり、場合によっては他の向精神薬を用いたりして、不安の緩和を目指します。精神療法では、特に効果が認められているのが認知行動療法(CBT)です。