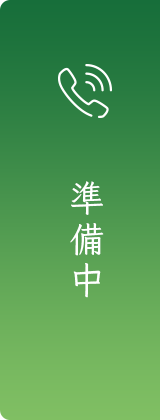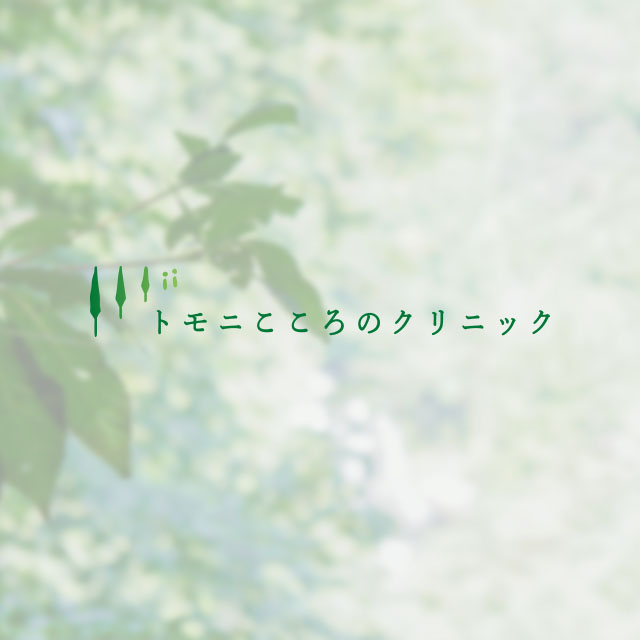はじめに
不眠は、誰にでも起こりうる身近なものです。睡眠薬などの不眠治療薬は、精神科だけでなく、内科や外科などさまざまな診療科で処方されることがあります。今回は「精神科以外で睡眠薬を処方されたときの注意点」について考えてみたいと思います。
私は睡眠医学の専門家ではありませんので、睡眠習慣の改善については睡眠専門の先生方の記事をぜひご参照ください。ここでは、精神科医の立場から、不眠の背景や注意すべき点をお伝えします。
なぜ不眠になるのでしょうか
原因のない不眠はありません。
不眠だけを薬で抑えるのは必ずしも良い方法とは言えません。実際には、次のような体の病気が原因で眠れなくなることもあります。
-
睡眠時無呼吸症候群
大きないびきや、睡眠中に呼吸が止まることがあります。息が止まると身体は「目を覚まそう」とします。無理に睡眠薬で眠らせるのは危険で、治療の中心は「呼吸を整えること」です。 -
周期性四肢運動障害
眠ろうとすると体がピクついてしまう病気です。この場合には、筋肉をゆるめる薬や、ドーパミンに関わる神経の働きを調整する薬を使うことがあります。
このような場合は、きちんと検査を受けて診断をつける必要があります。
不眠の種類はいろいろあります
身体疾患以外にも、不眠にはさまざまなタイプがあります。
-
神経症性の不眠
-
うつ病にともなう不眠
-
睡眠リズムの障害 など
そのため、「睡眠薬をもらえば解決する」という考え方はおすすめできません。
ただし、必ずしも大掛かりな検査が必要というわけではありません。精神科医であれば、多くの場合、不眠の背景を推測して対応することができます。難しいケースでは睡眠専門医に紹介して検査を受けることも可能です。
不眠の検査について
検査には ポリソムノグラフィ(PSG) という方法があり、
-
自宅でできる「簡易PSG」
-
医療機関に一泊入院して行う「フルPSG」
があります。これにより、不眠の正確な原因を調べることができます。
精神科医であれば、必要に応じてこうした検査が受けられる医療機関へ紹介することも可能です。
睡眠薬との付き合い方
睡眠薬の特徴は「出すのは簡単、減らすのは難しい」という点です。
自己判断で減薬を試みると、かえって眠れなくなり「やっぱり薬が必要だ」と戻ってしまうことが少なくありません。減薬を希望される場合は、必ず医師と相談されることをおすすめします。
まとめ
-
不眠は誰にでも起こる
-
背景には身体疾患や心の病気が隠れていることがある
-
睡眠薬は便利だが、やめどきや使い方には注意が必要
もし「眠れない夜が続いてつらい」と感じている方は、一度精神科や心療内科に相談してみてください。専門医と一緒に原因を考え、より安心できる眠りを目指していきましょう。